目次
【驚愕の離乳食革命】お粥より野菜スープが正解!?現役鍼灸師が語る、子どもの「生きる力」を育む新常識
こんにちは!「子供のココロとカラダを整える鍼灸師」として、ママの肩の力を抜く”ええ加減”育児を提唱している安村政子です。
いつもメルマガを読んでくださり、ありがとうございます!本日は、読者の方からいただいた離乳食に関する疑問にお答えするとともに、「ええ加減流」離乳食の真髄をお伝えしたいと思います。
読者K様からのご質問
安村様、初めまして。
いつもメルマガ読ませてもらっています。
野菜スープというのは、何種類か野菜を混ぜたものでいいのでしょうか?
初めて、口にさせる時は、アレルギーがあるかもしれないので、1種類から始めると思っていました。
現在6ヶ月の赤ちゃんがいるのですが、メルマガを読んでお粥ではなく野菜スープから始めようとしています。
お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。 K様より
K様、ご質問ありがとうございます!メルマガを読んで、お粥ではなく野菜スープから始めようとしてくださっているとのこと、本当に嬉しく思います。
【目からウロコ!】離乳食は「食べさせる」前に「育てる」が重要!
結論から申し上げますと、野菜スープは何種類か混ぜていただいて大丈夫です。人参、大根、玉ねぎなどの根菜は、優しい甘みと栄養がたっぷりなのでおすすめです。
そして、K様がおっしゃるように「アレルギーがあるかもしれないから、初めて食べるときは、一種類から」と思われている方は多いのですが、実は**「食べさせること」よりも前に「育てる」ことが大切**なんです。
なぜなら、赤ちゃんが食べ物を消化吸収するためには、消化酵素をしっかりと育てていく必要があるから。そのためには、適切な運動と質の高い睡眠が欠かせません。
なぜ「お粥から」がアレルギーのリスクを高めるのか?
「え、お粥から始めるのが当たり前じゃないの?」そう思われた方もいるかもしれませんね。
しかし、私がお伝えしたいのは、消化機能が未熟な赤ちゃんに、いきなり糖質の多いお粥を与えることが、アレルギーのリスクを高める可能性があるということ。詳しくは後述しますが、消化酵素が十分に育っていない状態で特定の食材を早期に与えることが、体にとって負担になることがあるのです。
「ええ加減流」発達に沿った離乳食の進め方【完全ガイド】
私の提唱する離乳食は、栄養面や調理法をお伝えするものではありません。あくまで、赤ちゃんの口の機能、消化、吸収、排泄、そして発達に合わせたもの。
「うちの子、なかなか離乳食を食べてくれない…」
「何から始めたらいいかわからない…」
そんな悩みを抱えるママ・パパは、ぜひこの先を読み進めてください。
【再確認】授乳姿勢と赤ちゃんの舌の動き、大丈夫ですか?
離乳食のスタートラインは、実はおっぱいを飲むときから始まっています。
新生児の舌の動き
生まれたばかりの赤ちゃんは、おっぱい(または哺乳瓶)を吸うとき、「吸啜反射」という本能的な動きをします。この時、赤ちゃんは舌を前から後ろへ動かし、お乳を搾り出して喉へ送り込んでいます。(舌の前後運動のみ)
【要注意!】逆嚥下をしている赤ちゃんが増えています!
もし、赤ちゃんが舌を後ろから前へと動かして(逆向きに)お乳を搾り出している場合、それは「逆嚥下」をしているサインかもしれません。常に舌が出ている赤ちゃんも、逆嚥下の可能性があります。
今すぐ授乳姿勢を見直してください! 一度間違った舌の使い方を覚えてしまうと、修正に時間がかかることがあります(当サロン比)。
生後2か月:味覚の基礎が育つ大切な時期
この時期、赤ちゃんは本能的に好きな味覚(生命維持に必要な基本的味覚、つまりおっぱいの味!)を育んでいます。
この時期にスプーンでスープなどを与えても、赤ちゃんはまだ口を閉じることができません。 無理に飲ませようとすると、口からこぼれてしまいます。赤ちゃんはまだ「乳児嚥下」(口を開けて飲み込む)の段階。焦らず、正しい舌の使い方を意識しましょう。
【NG行為】 赤ちゃんの体を傾けて無理やり飲ませようとすると、誤嚥やむせの原因になります。
生後3か月:口を閉じる練習と「なんだろう?」の探求心
生後3ヶ月頃までに、正しいラッチオンでしっかりおっぱいを飲ませることで、唇の筋肉が発達し、だんだん口を閉じて飲めるようになってきます。
また、この頃から「ハンドリガード」が始まり、赤ちゃんは何でも口に入れて「これはなんだろう?」と確かめ始めます。
【重要】飲み込ませるのではなく、「ガジガジ」させる!
この時期の赤ちゃんの胃はまだ竹筒のような形をしているため、吐きやすいです。無理に飲み込ませるのではなく、野菜スティックなどを持たせて、自由にガジガジさせてあげましょう。 これは食べる練習ではなく、口を閉じる練習です。
汚い、危ない、とすぐに取り上げるのではなく、安全な範囲で思う存分ガジガジさせてあげてください。口をしっかり閉じられるようになれば、自然と野菜スープを「すする」ことができるようになります。
生後7か月:「舌食べ」をマスターし、食べ物の選別能力を育む
7ヶ月頃は、舌で食べ物を押しつぶして食べる**「舌食べ」**をしっかりと経験させてあげてください。また、本能的に嫌う味覚(苦味など、毒物発見のための味覚)も育ってきます。
赤ちゃんが手を伸ばして欲しがるものを、スプーンの先に少しだけ乗せて、赤ちゃんが食べに来るのを待ちましょう。 ここで大切なのは「待つ」こと。もし食べに来ない場合は、授乳がうまくいっていない可能性も。赤ちゃんの舌の動きを観察してみてください。
【鉄分補給】 この頃から、母乳からの鉄分が減ってくるため、離乳食で鉄分の多い食材を取り入れることを意識しましょう。
舌の動きも、前後の動きに加えて、上下の動き(下から上に上げ、食べ物を上あごに押しつぶす)が活発になります。
また、たんぱく質・脂肪の消化酵素も増えてくるため、植物性たんぱく質のスタートに適した時期です。
生後9か月:「手づかみ食べ」で五感を刺激!歯ぐきで噛む練習も
さあ、いよいよ「手づかみ食べ」のスタートです!そして、「舌食べ」から歯ぐきで潰して食べる段階へと移行します。
与える食材は、指で軽くつぶせる程度の固さが目安。煮物をあえて潰さずに与えるのも良いでしょう。舌の動きは、前後・上下に加えて、左右の動きも加わります。
【言葉の発達にも繋がる!】 歯ぐきで噛むことで、言葉を発するための口周りの筋肉も発達します。
【最重要】前歯で「噛み切る」練習を始めよう! 前歯を使うことは、前頭葉の発達と深く関わっています。
歯が8本生えそろったら:いよいよ「ごはん」デビュー!
上の歯4本、下の歯4本が生えそろえば、お粥にする必要はありません。ここまでにしっかりと食べることを学んできているので、普通のご飯から始められます。
1歳半以降:噛む力を育てる大切な時期
奥歯が生えそろうにつれて、食べられるものがどんどん増えていきます。大切なのは、歯の状態に合わせて噛む力を獲得していくこと。
【NG】 早くから「カミカミしなさい!」と無理強いするのは、食いしばりを招くだけです。
2歳くらいまでに噛む能力をしっかりと育てましょう。 この時期に噛むことが苦手になると、将来的に偏食などの問題に繋がる可能性も。
【要注意】2歳までは糖質消化酵素が未熟! ご飯、うどん、パン、甘いものの与えすぎは、子どもの消化不良の原因になることがあります。
【まとめ】「食べない」と悩まないで!赤ちゃんの成長をゆっくり見守りましょう
お子さんが離乳食をなかなか食べてくれないと、本当に不安になりますよね。でも、どうか「食べさせなければ!」と焦らないでください。7ヶ月頃までは、栄養は母乳からしっかりと摂れています。
まずは、赤ちゃんの授乳時の舌の動きを意識すること。すべてはそこから始まります。
そして、消化酵素が未熟な状態で無理に食べ物を与えてしまうことが、アレルギーの原因になることも覚えておいてください。アレルギーは、生まれつきのものではなく、発達状態を無視した離乳食の進め方が引き起こす可能性があるのです。皮膚炎も、呼吸の問題と深く関わっていますよ。
もし、もっと詳しく離乳食の進め方について知りたい、個別で相談したいという方は、ぜひ当サロンにお越しください。目から鱗の情報が満載ですよ!

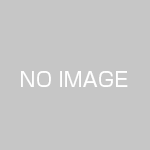









この記事へのコメントはありません。