子どもの健康を姿勢から守る「ええ加減」育児の安村政子です。
「うちの子、どうしていつもお口が開いてるんだろう?」
そう思ったことはありませんか? 赤ちゃんは生まれたばかりの頃こそ鼻呼吸ですが、いつの間にか口呼吸になっているお子さん、実は多いんです。
お口が開いていると、見た目が少しぼーっとした印象になるだけでなく、お口の中が乾燥して虫歯や風邪、アレルギーの原因になったり、お顔の形にまで影響が出たりすることも!
もしかして、こんなお悩みありませんか?
いつも口がポカンと開いている
柔らかいものしか食べられない
丸飲みする癖がある
少しでも固いと口から出してしまう
この記事では、「赤ちゃんは口を開けていて当たり前」「噛むことができなくても仕方ない」と感じているママに、実は赤ちゃんはちゃんと口を閉じることができる、そして噛む力も育てられるということをお伝えします。ぜひ、読み進めてみてくださいね。
目次
【要注意】赤ちゃんの口が開いている? 赤ちゃんの口が閉じない?
先日、抱き方講座にご参加くださったママから、こんな嬉しいご感想をいただきました。
昨日抱き方姿勢講座を受講した〇〇です。
お忙しいところ、個別相談の内容も盛り込んでいただき、本当にありがとうございました。子どもの世話をしながらの参加で、お話がしづらい場面もあったかと思いますが、申し訳ありませんでした。
これまで、「赤ちゃんは口を開けているのが普通」「子どもは噛めなくて当たり前」と思っていたことが、実はそうではないと教えていただき、本当に驚きました。先生のお孫さんの動画を見て、生後8ヶ月でもあんなにしっかりとした力が出せることに感動し、最初に教えることの大切さを痛感しました。
モンテッソーリ教育や伊藤美佳先生のメルマガなどで、自分なりに勉強しているつもりでしたが、全く理解できていなかったことに気づき、大きな衝撃を受けました。授乳姿勢の改善と泣くトレーニング後の赤ちゃんの写真を見せていただいた時の変化にも、本当に驚きました。
まずは、できることから、授乳姿勢を見直してみようと思います。もし動画撮影できたら、ぜひ送らせてください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
〇〇さん、素敵なご感想ありがとうございます! 「口を開けているのが当たり前」「噛まなくて当たり前」という認識が変わったとのこと、本当に嬉しいです!
お子様の成長は、これからが本番です! ママのちょっとした関わり方次第で、お子様の持っている素晴らしい能力はどんどん伸びていきますよ。
では、なぜ日本では口を開けている赤ちゃんが多いのか、そして噛まない赤ちゃんが多いのか、その理由と改善策について、詳しくお話していきましょう。
え、当たり前じゃないの? 口ポカーンは抱っこの仕方から始まる
日本では、お口がポカーンと開いている赤ちゃんをよく見かけますが、「それが良くないことだ」と認識している方は、残念ながらまだ多くありません。「え? 赤ちゃんって、みんな口を開けてるんじゃないの?」そんな声が聞こえてきそうですね。
しかし、驚くことに、海外では日本の赤ちゃんの口が開いている様子を見て、「どうして?」と不思議に思う方が多いそうです。あなたはご存知でしたか?
健康を害するのに、どうして開けさせるの…WHY?
日本人の口呼吸に対する意識の低さは、比較的安定した気候も影響しているかもしれません。海外には、日本と違って寒い国、暑い国、乾燥がひどい国、砂塵が舞う国など、厳しい環境の国が多く存在します。実際に、口呼吸による健康被害も多いため、「口呼吸は良くない」という意識が非常に高いのです。
なんと、赤ちゃん自らが口を開けないようにすると言います。それでも開けてしまう赤ちゃんには、おしゃぶりを使わせてまで口を閉じさせる国もあるほどです。砂埃のひどいドバイでは、6歳までおしゃぶりを使うのは一般的なことだそうですよ。
一方で、現代の日本の気候はどうでしょうか? 四季の変化は曖昧になり、花粉症はもはや国民病と言えるほど蔓延しています。決して、油断できる環境とは言えませんよね。
赤ちゃんは本来、口呼吸をしない
生まれたばかりの赤ちゃんの気道は、まだ完全に形成されていません。気道や喉は、成長の過程で作られていくのです。一般的に、気道がしっかりと機能し始めるのは、食道にある2つの弁のうち1つが閉じる生後3ヶ月頃と言われています。
ですから、それまではたとえ口が開いていても、多くの赤ちゃんはしっかりと鼻で呼吸をしています。
まあるいCカーブの姿勢がポイント
お腹の中でまあるいCカーブを描いていた赤ちゃんは、生まれて肺呼吸に変わっても、舌(ベロ)が上あごにくっついた状態を保っています。そのため、口が開いていても、お口の中はほぼ密閉された状態になり、口呼吸にはなりにくいのです。
ちょっと試してみてください! 舌を上あごにしっかりとつけた状態で、口から息を吸ってみてください。どうですか? 口から空気は入ってきませんよね?
抱っこの仕方で、舌の位置は変わる
舌を自動車に例えるなら、上あごは駐車場です。顎が上がった不安定な抱き方をしてしまうと、舌は自然と下がりやすくなってしまいます。
もし、正しい抱っこをしているのに舌が下がってしまう場合は、舌自体に何らかの問題があるか、授乳時にしっかりと舌を使っていない、または舌を使いにくい姿勢になっている可能性が考えられます。
舌の位置は、赤ちゃんの首のすわりと深く関わっています。正しい舌の位置を知るためにも、正しい抱っこの仕方を学ぶことを強くおすすめします。
お粥から始めない! 離乳食で噛む力を育てる
生まれたばかりの赤ちゃんは、原始反射である乳児嚥下によって、誰に教わるまでもなくおっぱいを吸うことができます。
乳児嚥下と大人の嚥下(成人嚥下)の大きな違いは、簡単に言うと、「乳児嚥下は水分を飲むための飲み方」「成人嚥下は固形物を飲み込むための飲み方」です。生後約6ヶ月という限られた期間に、赤ちゃんは「反射で飲む(乳児嚥下)」ことから「自分の意志で飲む(成人嚥下)」へと、成長とともに学習していく必要があります。
しかし、離乳食を始める際に、食べ物に水分を多く含ませて与えてしまうと、赤ちゃんは乳児嚥下のまま飲み込んでしまい、成人嚥下への移行がスムーズにいかなくなります。
噛むことを教えるのは、おっぱいから
赤ちゃんに「噛む」ことを教えるのは、いつからだと思いますか? 実は、おっぱいを飲ませるその瞬間から始まっているのです。先日、口育士協会でも発表がありましたが、「噛むことを教える最初の時期」は、まさに授乳の時なのです。
あなたは、赤ちゃんがおっぱいを飲む時に、しっかりと噛むように飲ませていますか?
乳首だけではなく、乳輪部分まで深く咥えさせ、おっぱいを噛むように意識して授乳してみましょう。そして、離乳食はお子様の「お口の発達」を促す大切なステップとして捉え、始めてみませんか?
ペースト状のお粥からスタートしてしまうと、お子様の噛む力はなかなか育ちません。もちろん個人差はありますが、飲むこと(哺乳)から食べること(咀嚼)へスムーズに移行するためには、歯茎でつぶせる程度の柔らかさで、ある程度の大きさのあるものを最初から与えることをおすすめします。
最近では、小児科の先生の中にも、 (10倍粥) に反対する意見が増えてきています。
いかがでしたでしょうか? 今回は、赤ちゃんの口呼吸と噛む力の発達についてお話しました。「うちの子は大丈夫かな?」と少しでも気になった方は、ぜひ今日から抱っこの仕方や授乳の方法を見直してみてください。
お子様の健やかな成長のために、私たち「ええ加減」育児はこれからも精一杯サポートしていきます!

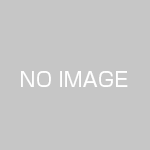











この記事へのコメントはありません。